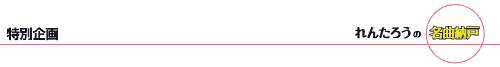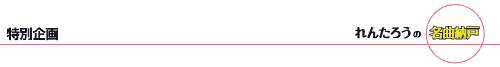以前、知り合いのHPのBBSで「大滝詠一の最大の魅力は?」という話題が上った時、僕は迷わず「歌唱」と答えました。その時の他の人の対応は「へっ?」って感じのもので、やはり「サウンド」や「メロディ」、「豊富な音楽的知識に基づく楽曲作り」といった答えが多かったように思います。最近は健太さんなども言っていることなので、別に声を大にして発表することではないのですが、ナイアガラ・ファン歴20年を越え最近つくづく感じることは「大滝詠一の魅力は歌唱に尽きる」ということなのです。
僕の初の大滝体験は1982年、バスケの練習に明け暮れていた中学2年生の頃でした。バスケ部の松井くんの家に練習の後に遊びに行き、『ロンバケ』を聴かされたのです。当時ニュー・ミュージックが好きな普通の少年だった僕は「これ、新人?」と松井くんに質問したのを覚えています。なぜこんな質問をしたかというと正直あまり覚えていないのですが、今思えば、声は若々しいのに妙に玄人っぽい印象を受けたからだと思います。そして次の瞬間には、この「大滝詠一」という人の作る音楽を好きになっていました。もちろん当時はまだスペクターもキング&ゴフィンも知らないわけですから、『ロンバケ』のサウンドやメロディの奥深い魅力など到底理解できるはずはなく、若者特有の生理的な感覚だけで「この音楽、気持ちいい!」と感じたのだと思います。
その後すぐにレコードを買い、それこそ猿のように毎日毎日『ロンバケ』を聴き続ける日々が始まります。僕の当時の聴き方と言えば「聴く」というよりむしろ「歌う」と表現した方がいいくらい、レコードに合わせて一緒に歌っていたのです。その後『All About Niagara』などの書籍、オールディーズのレコード等を集めることによって正しいナイアガラーとしての道を進んでいくことになるわけですが、それは松井くんの家で何も知らないまま体験したあの快感は何だったのか?ということを見つけようとする行為だったのかもしれません。そして見つけたこと、それは膨大なポップスの遺産の中から摂取した要素を巧妙に組み立て、サウンドとメロディとリズムを奇跡的なバランスで形作るという研究を日々続けたマエストロの姿でした。
そして全てのナイアガラーに洩れず、僕もその研究の確認作業(俗っぽく言えばネタ探し)に没頭する日々が続いたのです。そこで見つけた数々のポップスの黄金比は僕の大切な宝であり、今もいつでも戻るべき原点としてしっかり存在しています。しかしそれで松井くんの家で体験した快感理由が全て判明したかといえばそうではなく、何か大事なものを忘れているような気がしていたのです。
それこそが「大滝詠一の歌唱がもたらす快感」だと気付いたのはつい最近のことでした。
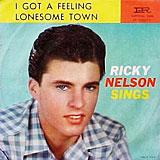 3年ほど前の、あるクリスマス・パーティの席上、リッキー・ネルソン(Ricky Nelson)の「ロンサム・タウン」(Lonesome Town)のSP盤を蓄音機で聴くという機会に恵まれました。時代の闇から生々しく蘇ってくるその声に、僕は無垢な響きを感じ感動を覚えました。音楽史的なことから見ると、50年代後半というアメリカが一番豊かで幸せな時期に生まれた曲であり、その時代性が声に無垢な響きを持たせているのかななんて思ったりもしましたが、どうも自分の中に未だ辛うじて残っている無垢な感性(僕の中の少年?)に響いたようなのです。なぜならそれは大滝氏の声と歌い方に、異常に似ていたからであり、中学生という無垢な年頃に初めて『ロンバケ』を聴いた時のあの感覚が蘇ったというわけです(そういえば『A LONG VACATION』というタイトルも、もともとはリッキー・ネルソンの曲のタイトルから頂いたものでしたっけ)。
3年ほど前の、あるクリスマス・パーティの席上、リッキー・ネルソン(Ricky Nelson)の「ロンサム・タウン」(Lonesome Town)のSP盤を蓄音機で聴くという機会に恵まれました。時代の闇から生々しく蘇ってくるその声に、僕は無垢な響きを感じ感動を覚えました。音楽史的なことから見ると、50年代後半というアメリカが一番豊かで幸せな時期に生まれた曲であり、その時代性が声に無垢な響きを持たせているのかななんて思ったりもしましたが、どうも自分の中に未だ辛うじて残っている無垢な感性(僕の中の少年?)に響いたようなのです。なぜならそれは大滝氏の声と歌い方に、異常に似ていたからであり、中学生という無垢な年頃に初めて『ロンバケ』を聴いた時のあの感覚が蘇ったというわけです(そういえば『A LONG VACATION』というタイトルも、もともとはリッキー・ネルソンの曲のタイトルから頂いたものでしたっけ)。
リッキー・ネルソンに限らず、例えばブライアン・ウィルソン(Brian Wilson)が「Surfer Girl」の後半で聴かせる「little one ahh〜」のファルセット・ヴォイスや、ロイ・オービソン(Roy Orbison)が「Blue Angel」のブレイク部分「I'll love you till the end of time」の「ti〜〜〜me」のヨーデル風歌い方に、胸を掻き毟らされるほど甘酸っぱい瞬間を感じることがありますが、大滝氏のヴォーカル(声質そのものと歌い方、両方)には正にその「甘く切ない」感覚がしっかり宿っていると思うのです。
例えば「カナリア諸島にて」での「薄く切った オレンジを〜」の「オ」の鼻腔に抜ける感じや、「我が心のピンボール」の「はにかみやが愛の唄を作り〜〜」の「り〜〜」のコブシ、同様に「オリーブの午后」の最後「君の寝顔にみとれてもいいだろう〜〜」のファルセットなど、ただ単に耳に快感を与えるだけの技巧としての巧さの奥に、無垢な響きや切ない感覚が含まれているのを感じます。それはリッキー・ネルソンやブライアンに直結するものであり、大滝氏の「声質」といった先天的なものに加え、長いポップスの研究の上に学び取った「感覚」と「技巧」がそのように演出をさせているのだと思います。僕がアホのように毎日『ロンバケ』を聴きながら一緒に歌ったのは、その「感覚」と「技巧」がもたらす快感を自ら参加して味わいたかったからだと思うのです。
 ナイアガラーは大ざっぱに『ロンバケ』以前と『ロンバケ』以降に分かれると思いますが(世代のことではなく、好き嫌いの話)、自分が『ロンバケ』以降派だと思う最大の理由として、やはりヴォーカルの魅力を満喫できるのは圧倒的に『ロンバケ』以降だからなのです。大滝氏本人も『ロンバケ』は「青春歌謡アルバム」みたいな言い方をしていたと思いますが、『ロンバケ』以前はサウンド、リズムの実験に手一杯でヴォーカルまで手が回っていない印象を受けます。唯一『ロンバケ』的快感が得られるのは『夢で逢えたら』でのシリア・ポールとのデュエットか、「ブルー・ヴァレンタイン・デイ」くらいでしょうか。レーベル・プロデューサーとして様々なバランスに固執していた大滝氏ですが、音楽を構成する要素としてのメロディ、サウンド、リズムなどのバランスは除々にとれていき、『カレンダー』でほぼ完成をみています。しかしヴォーカルという要素が加わった完璧なバランスは『ロンバケ』まで待たなければならなかったというのも、ちょっと不思議な気がします。
ナイアガラーは大ざっぱに『ロンバケ』以前と『ロンバケ』以降に分かれると思いますが(世代のことではなく、好き嫌いの話)、自分が『ロンバケ』以降派だと思う最大の理由として、やはりヴォーカルの魅力を満喫できるのは圧倒的に『ロンバケ』以降だからなのです。大滝氏本人も『ロンバケ』は「青春歌謡アルバム」みたいな言い方をしていたと思いますが、『ロンバケ』以前はサウンド、リズムの実験に手一杯でヴォーカルまで手が回っていない印象を受けます。唯一『ロンバケ』的快感が得られるのは『夢で逢えたら』でのシリア・ポールとのデュエットか、「ブルー・ヴァレンタイン・デイ」くらいでしょうか。レーベル・プロデューサーとして様々なバランスに固執していた大滝氏ですが、音楽を構成する要素としてのメロディ、サウンド、リズムなどのバランスは除々にとれていき、『カレンダー』でほぼ完成をみています。しかしヴォーカルという要素が加わった完璧なバランスは『ロンバケ』まで待たなければならなかったというのも、ちょっと不思議な気がします。
日本では歌謡的なものしかウケない土壌があるので、ウケるために(売れるために)敢えて「歌謡アルバム」であるところの『ロンバケ』を作ったと、これまた本人が言っていましたが、しかしただの「歌謡アルバム」であるはずの『ロンバケ』には、60年代に聴きまくり70年代に実験しまくったポップスのエッセンスが「歌う」という行為に対してもしっかりと根付いています。そしてそれをようやく分かりやすい形でアピールしてくれたということ、『ロンバケ』の魅力とはまずそこなのではないか、引いては大滝音楽の最大の魅力もそこなのではないか!というのが僕個人の見方なのです。
作曲、プロデュース、CD監修、ラジオDJ、音楽評論…。様々な音楽表現を展開してきた大滝氏。何はともあれ再び「歌う」という、音楽表現の最前線に出てきてくれて嬉しい限りです。どんなに本人が嫌がろうとも(笑)、僕は大滝詠一のヴォーカルに「打ちのめされっ放し」なのですから。